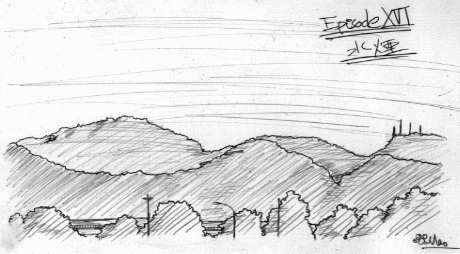
Episode XVI : 水煙
|
毎年のことではあるが、あたしの年中行事になっているその日のための準備はと言うと、相も変わらずかなりの重装備になってしまう。あたしは朝ご飯を済ませると、クローゼットや靴箱の奥から、少し手間取りながらその装備を引っ張り出した。 そして、一年ぶりのご対面に、ついしみじみと見てしまう。 「ふぅ……たまに使わないと埃だらけだよね」 つい独り言。用意した布きれで軽くはたいてやると、あたりがあっという間に埃っぽくなる。そばにいたベータが嫌な顔をしながら、つい、といなくなってしまった。 あたしが準備したのはこんな感じだった。まず踝の上まである古くなった登山靴。それから厚手で頑丈な長袖長ズボン、軍手、首の回りに巻くタオル。納屋から鉈とナイフ、杖も出してくる。そして、みごとな青空から降り注ぐ午前の陽の光に、少しだけカビ臭くなっているその品々を晒しておく。 湿気と臭いが飛ぶまでの間に、簡単な弁当とお茶を用意する。準備と言えばそれくらいで、装備の割に荷物は簡単だが、全部をそろえるにはそれなりの時間をとってしまう。 とはいえ、朝早くから始めたおかげで、一通り終わっても出発までにはまだ時間がある。どうせだからと店の回りの落ち葉も一通り掃き清めた後、箒を持ったまま、いま掃いたばかりの道に落ち葉が舞い落ちる様子を見ながらのんびりしていると、不意にアキオがやってきた。 「あれ、今日はお店休みだよ」 「……そやったっけ。なんかこのごろ曜日の感覚が変やわ」 「本見てってもいいけどね。開ける?」 「まぁ、ええわ。別に無理してまで欲しい本あるわけちゃうし」 アキオはバイクのエンジンを止めると、スタンドを立てて小さく背筋をのばした。あたしの隣に腰掛けようとしたのか、そこから一歩踏み出したとき、二階の窓から屋根に出してある例の装備に気づいたようだった。 「なんやねん、あれ。みょーなもん干して」 「あ、あれ……ちょっとね」 「山登りでもするんか? えらい本格的やな。みかげ、そんな趣味あったんか?」 「う、うん……」 あたしが少し曖昧な返事をしているのに気づいたのだろう、アキオは変な顔をしながらなにやら考えている様子だ。場の空気をごまかそうと何か言おうとしたあたしより一瞬はやく、アキオが口を開いた。 「先生がらみやろ」 「……う……ま、まぁね」 「みかげが普段と違うことしとうと、まぁ先生と関係やうからな」 「…………」 確かにアキオの言うとおりだ、そんなことを考えながら、あたしは小さくため息をついてしまう。 もっとも、普段と違う、というわけでもない。これはずっと年中行事だった。ただ、昔は先生と二人だけで、そして一人暮らしになってからはあたし一人だけでやってきた、それだけのことだ。 別に隠すようなことでもない。盂蘭盆の迎え火と一緒で、なんとなく一人でゆったりしたいだけの話なのだが……。 「今日やろ」 「え? うん」 「どこまで行くねん」 「その、すぐそこまでだよ。一時間ちょっとかかるかな」 「ほならオレも行くわ」 「…………」 結局、こうなってしまう。あたしはまた、小さくため息をついてしまった。 まぁ、アキオが先生に関係したことに興味を持つのはいつものことだ。それに、わざわざ断るほどのことでもない。無理をしてまで一人でいるよりは、ここは素直にアキオの気持ちを汲んであげるべきだろう。 「いいけど、お昼ご飯、一人分しかないよ」 「そこらでなんか買うてくるわ」 「あと、その格好じゃ無理だよ。重装備で来ないと」 「なにがあったらええねん。ウチ帰ってとってくる」 「……分厚い靴と軍手と帽子、それから鎌と杖と、そんなものかな。藪漕ぎになるからそのつもりで来てよ」 「わかった。すぐ戻ってくるわ、待っててや」 アキオが大急ぎでバイクに飛び乗ってクランクレバーを蹴っているのを、あたしはなんとなく眺めていた。 出発は昼前。徒歩で店を出発したあたしたちが、信号の交差点の少し北にある古い駅舎跡に差し掛かったとき、アキオはどこか引きつった顔になった。 「な、なぁ、ここってもう道ないんやろ」 「うん。でもここからしか行けないよ」 「……みかげの言うてたことの意味、わかったわ」 アキオが言っているのは、駅舎跡の下をくぐる古い道のことだった。 もう使う人もなくなった道。コンクリートの壁で挟まれた空間と地面に残ったわずかなアスファルトの跡で、初めてそこに道があったと気づかされるような場所。見慣れているはずのあたしでも、ここを歩くとなると一瞬、躊躇する。 地面はもう、湿気や日影を好む様々な草で一面に覆われている。もっとも、彼らは背があまり高くないから、駅舎の下に入り込めば、そこが確かに通れる場所であることが見て取れる。この風景が、これから歩く場所がどんな様子であるかを暗示している。 少しだけ自分に気合いを入れ、あたしは茎の柔らかな草を踏みながら暗がりの中に入っていく。アキオは少しだけ躊躇したが、すぐに後をついてきた。 短いトンネルはすぐに通り抜けてしまう。そこから光の中に出ると、アスファルトの痕跡はまだ沢沿いに続いている。先ほどとは違い、日当たりの良くない切り立った斜面に挟まれてきたせいだろうか、道そのものはかなり歩きやすくなっている。緩い上り坂を登っていると、右手に何件かの建物の跡がある。かつては誰かの住居であったのだろう、そのコンクリートの壁は、乾いて金色になった草の間からそっとこちらをのぞいている。 「こんなとこにも家、あったんやな」 「うん。この先にも少しあるよ。みんないろんなとこに住んだんだね」 にぎやかだったあの時代ですら、ここは市街地からはずれた奥まった場所だ。本当に人は、色々なところに住む。あたしが「みやこ」へ行く途中によく寄るあの展望台の周囲だって、あんな高い山の上だと言うのに、昔はたくさんの家が建っていたのだ。 なんだか不思議な感慨にふけってしまう。 しかし、そんな様子もすぐに終わる。道を登るにつれ、右手を流れている川との落差が大きくなり、やがてその川を渡る橋にさしかかると、そこから先にはもう、建物はない。 「よかった、今年もまだセーフだね」 その橋をわたる前、あたしがそう言うと、アキオが少し目をしばたたかせる。 「え? なにがや?」 「橋だよ。ここが渡れなくなったらもう、先に行けないからね」 「……せやけど、立派な橋やんか。まだまだ平気やろ」 「うん。でもここらへんて地盤がよくないでしょ、いきなりダメになっちゃうこともあるからさ。それより、ここから先は大変だよ。気をつけてね」 「そ、そか。わかった」 あたしがけして、アキオを脅かそうとそんなことを言ったわけではないことは、彼にもすぐにわかったようだった。 橋を渡ってすぐは、まだ道はしっかりしている。急な崖の一部を削って作られたアスファルトの道は、継ぎ目や割れ目からたくさんの草が生えたり、右手の斜面から崩れてきた石が少し散らばっているくらいで、特別歩きにくいわけではない。 が、それも少しの間だけだ。道は突然、まったく唐突に森の中に消えていた。 あたしはそれが、昔はそこから山道になっていたためだと知っていたが、それを知らないアキオにとっては、まるで何のために道がついているのか、と首を傾げてしまうような光景だろう。 「さて、ここから装備が役に立つからね」 「……ほんまやな」 「さ、気合い入れていきましょ〜」 「ふぇ〜い」 腰まである絡み合った草を見たアキオは、なにやら情けない返事をした。 正直言うが、山刀など使う機会は年に何度もない。ただ草を刈るなら鎌で充分だ。しかし、蔓やら茎の強い草やらがゴチャゴチャになって、表面が一枚の布のようになった草を切り開くにはやはり、長くて重みがある山刀がないとどうしようもない。 まるで手慣れたような顔をしているあたしだったが、正直、重い山刀はかなり持て余しぎみだ。気をつけていないと自分の足を切ってしまいそうになる。 もちろん、道の全部がそんな状態ではない。谷間に鬱蒼と多い繁った木々の影で、昔一度は踏み固められた道は歩くのに不自由はない。しかし、場所によっては、みごとに伸びた一年分の草に足止めされる。 アスファルトが終わって少しの間、道は平らになっているが、そこはまさに、そういう部分にあたっている。もともと公園だったと言うが、開けた空間が余計に草を元気づけている様子だった。 進むのにかなりの時間がかかる。時々足を止め、山刀を振り、軍手をした手で左右に分け、足で踏む。あたしが進むと、アキオも同じように手と足を使ってすぐ後ろをついてくる。ちょっとした距離でも、普通に道を歩くより何倍も時間がかかる。ただ黙々と、自分で道を作りながら進むしかない。 しばらく進むうちに、アキオが不意に立ち止まった。気配ですぐにそれがわかって振り返ると、なにやらあたりに耳を澄ませている様子だった。 「この音……川の音ちゃうやろ」 「ん? もう聞こえるんだ」 「オレ、耳だけはええねん」 あたしも足を止めて、試しに耳をすませてみる。なるほど、じっとしていると、遠くから響いてくる、さぁっ、という音がわかった。 アキオはまだ、じっとその音を聞いてるようだった。そして何度かあたりを見回した。 「もしかしてな、変なこと言うかもしれへんけど」 「なに?」 「滝とちゃうか」 「そだよ。このすぐ先に一つあるから音が聞こえるんだよね。すぐそばを通るから見えるかな」 「…………」 「どしたの?」 アキオの顔を見ると、なにやら驚いた表情を見せている。それがおかしくて、あたしは小さく吹き出してしまった。 「なんやね。誰かて驚くやろ」 「そうかなぁ。こんな地形なんだから滝くらいあったって変じゃないと思うけど」 「そ、そらそやけど、すぐそこやんか。こんな近いとこにあるなんて思えへんかってん」 「そうかなぁ。ま、この先でそばを通るから。木の間だから少し見えにくいけど」 はたして、道を進むについて音ははっきりと耳に入るようになり、不意に左手の崖の下に水しぶきの白い影が見える。アキオは何度か身を乗り出すようにして、その姿に見入っているようだった。 滝と行っても、実際のところ、それほど大きいわけではない。眼下の滝は切り立った岩壁の間を滑り落ちていて、それはそれで絶景だったが、迫力という点ではあたしが「滝」と聞いて想像する光景とはかなり差があるのは確かだった。 それでもアキオは、足を止めてその様子を見ていた。あたしは休憩がてら、そんなアキオが動き出すのを、道端の石に軽く腰掛けて待っていた。 「アキオってほんとに、滝は見たこと無かったんだね」 「こんなとこにあるなんて、知っとったらすぐにでも見にきたわ」 「ふぅん……」 あたしが少し含みのある笑いになると、アキオは少し変な顔であたしを見た。そして、あたしが何を言いたいのか量りかねたようで何度か瞬きをした。 「今度はなんやね」 「うん、ちょっとね。まぁ、この先を楽しみにしといて」 アキオが滝を見ていたのは数分のことだったろうか。再び道を先に進み始める。 滝から少し進むと、道は右に折れ、急な斜面を登り始める。先ほどまでの空き地とは違い、草のほうはそれほどでもないが、土の弱い斜面を這うように登るのは別の苦労だ。 何度か、崩れた土の上を歩くことになる。ここから転落すれば冗談ごとではすまされない。そういう場所は、たとえ手間がかかっても、足で土を踏みしめ、道を作りながら上るしかないが、グズグズになった地面はなかなかそれを許してくれず、かなり苦労させられる。 所々不意に、昔の道の跡に出くわす。と言っても、ほんの少しの幅しかない、ほとんど獣道と言っていいような道だ。それでも踏み固められた道は歩きやすさは全然違う。 「ま、待ってや〜」 あまりの急斜面にアキオがまた情けない声を出している。かなり息も切れているのがわかる。 「ここだけだから……。もうちょっとで楽になるからさ」 そう言っているあたしも、正直、かなり息を切らしている。しかし、ここがいちばん大変な場所なのは確かだ。 数分で、細い道は別の、やや整備された道……と言っても、足下は岩だし、幅も少し広くなったと言う程度だ……に出る。左手は山を登ってゆき、右手は下ってゆく。あたしは左手の登りのほうに少しだけ入ると、やっと足を止めた。 「こんなキツいんやったら、最初から言うてや……」 「ほんとにここだけなんだってば。少し休んでこ、もう少し距離あるから」 「うん……」 呼吸が整うまで、あたしたちは道ばたに座り込んでいた。滝の音はかすかに聞こえるだけ、それよりも周囲には、柔らかな葉擦れの音や鳥の声が満ちている。 「だんだん紅葉が強くなってるよね」 不意にあたしが言うと、アキオは顔を上げて周囲を見回した。 「ほんまや。街のほうやとここまで紅葉してへんやろ」 「ま、六甲山系は曲がりなりにも千メートル級の山だしね。もう少し登るから、もうちょっときれいになると思うよ」 「ま……まだ登るんか……?」 疲れた顔のアキオをほっといて改めてあたりを見ると、切り立った渓谷を包むややくすんだ色の木々の中に鮮やかな黄色や赤が混ざり始めている。ここまできれいなのは何年ぶりになるだろうか。このぶんだと、目的地のほうはかなり期待できそうだ。 「よし、出発!」 「そやな〜」 あたしが歩き始め、アキオがついてくる。ここからは足下もかなり硬く締まっていて、草はそれほど生えていない。右手の急な斜面が少しずつ崩れて道を狭くしているが、ほとんどの場所は通れないというほどでもないし、その斜面も風化した岩で、草はほとんど生えない。ただ所々、かなり以前に崩れた岩の間から生えた草たちが行く手を遮り、再び用意した装備の出番となる。 また滝の音が近づく。アキオは何度も立ち止まり、左手の崖の下をのぞき込んでいるが、木々に遮られてほとんど見えない。あたしは、この下にももう一つ滝があることを知っていたが、敢えてそのまま先を進んだ。 結局、水音の源を確かめられなかったアキオは、少しだけ眉を寄せながらあたしのあとをついてきた。 道の調子は相変わらず。少なくとも最初の急斜面ほど歩きにくくないのが幸いだ。そのまま小半時ほど歩いただろうか、前方の渓谷の間から、別の水音が聞こえてくるのを、アキオは聞き逃さなかった。 今度の音はかなり力強い。その気配は山肌の向こうからもひしひしと伝わってくる。さらに鮮やかさを増した紅葉の間から、何か強い意志のようなものを感じる。 もう目的地が近いことを、アキオは敏感に感じ取ったようだった。遅れ気味だった足取りもしっかりして、今はあたしのすぐ後ろを歩いている。 道の傾斜がゆるんできたことも手伝い、歩みは少し速くなっている。水音はさらに強くなる。 ある曲がり角を出たととたん、唐突にそれはあたしたちの視界に姿を現した。 そしてその瞬間、アキオはぽかん、とした表情で立ち止まった。 はるか上空から降り注ぐ一本の水柱。数十メートルはあるかと思える急峻な崖の一角から水煙を立てながら一筋の水が流れ落ち、途中、何度か岩肌にぶつかりながら滝壺に流れ込んでいる。とうとうと、絶え間なく流れる水は、まるで生きているかのようにかすかに踊り、岩肌に不思議な彩りを添えている。 その下の滝壺の色。緑がかった深い深い青。見ていると吸い込まれそうになる。岩の灰色、水の白、滝壺と空の青を、見事に紅葉した木々の色がくっきりと際だたせる。 それまでの急斜面からは想像も出来ない、崖に囲まれた広い空間が空に向かって立ち上がっている。その広さが何か、開放感のようなものを与えてくれる。 ああ、やっぱり来てよかった、あたしは心の中でそうつぶやいた。 それに今年の紅葉。想像していた以上に綺麗だ。これまで何度も訪れたこの場所、あたしの中に強い印象をもたらすその風景にも、新たな感慨が加わる。 ちょっとの間、その印象を全身で受け止めている。つい、顔には笑みが浮かんでしまう。 「さ……」 あたしはひとつ、大きく息をすると、アキオを振り返った。いつまでもここに立っているわけにもいかないだろう。アキオがまだそこでじっとしているのにあたしはつい小さく笑ってしまうと、再び彼に声をかけた。 「その先で広い場所があるからさ、お昼にしよ」 「……そ、そやな……」 あたしが言った通り、そこから少しだけ進むと、滝壺に面してデッキが備え付けられている。もともと滝を見るために作られた場所だ、そこからはさらに滝の全貌があらわになる。 「さぁ、おなかすいちゃったよ」 「…………」 あたしが、ベンチ代わりの岩の一つに腰掛け、リュックを降ろすと、アキオがそのそばにやってくる。しかし彼は岩には座らず、デッキの手すりにもたれかかり、身を乗り出すようにしてまだ舞い落ちる水の流れを見つめていた。 「先に食べちゃうよ」 「あ、ああ……オレ、もう少しこれ見てからにするわ」 「うん……」 あたしはリュックの蓋を開き、中を手探りするが、それでもなんとなくあたりに視線を走らせていた。 簡単なお弁当を取り出し、なんとなく蓋を閉じたままゆっくりしている。デッキをうろうろしているアキオのほうをつい見てしまう。 「ほんまに知らんかったわ、こんなとこ」 「まぁ、距離は近いけどけっこう山奥だからね。ちゃんとした道を作らないと、とても来れないよね」 「なぁ、みかげ。ほんまはこんなとこ、ほかにもあるんちゃうか」 「さぁ……。あたしはここしか知らないし。昔の道もどんどん使えなくなってるからね、探したらいろいろあるかもね」 「…………」 ようやくアキオは満足したのか、あたしの隣にやってきて腰を下ろした。あたしもやっとお弁当に手をつける気になって、蓋をとると特製のサンドイッチを取り出す。 「もうちっとマシな食べ物(たべもん)持ってくればよかったわ」 「ま、ここなら何食べてもおいしいけどね。あたしの少し食べる?」 「え、ええわ。悪いしな」 「んと、ここが雄滝(おんたき)っていうとこで、さっき下にもあったいくつかの滝をあわせて布引(ぬのびき)の滝って言うんだって」 「ふぅん……」 「なんか、華厳の滝(注16)とか那智の滝(注17)と並んで日本の三大神滝って言われてるみたいだけど、どうなんだろね」 「……ってゆうと、こんな滝がまだある言うこと?」 「あ、華厳の滝は「とちぎの国」のほうだし、那智の滝は「わかやまの国」のほうだから全然遠くだよ。それに迫力だけならこの二つのほうがずっと上なんだよね。三大って言うわりに、布引の滝ってけっこう小さいんだよ(注18)」 「…………」 「けどあたしは、ここが一番好きだな。なんかすごく雰囲気があるし」 「…………」 あたしに続いて簡単な弁当に手をつけ始めたアキオは、それでもまた滝壺のほうに目を向けている。なにかをじっと考えている様子。そんな彼を邪魔しないよう、あたしは黙っていた。そうして、しばらく、黙々と食べ物を口に運んでいる。 それが一段落すると、不意にアキオが言った。 「ここも先生がらみやろ」 「……わかる? 先生ってここの紅葉が大好きなんだって。それで毎年、山が色づいたらここに来てたんだ」 「……それ、わかるわ。せやけど先生、ええ場所見つけんの、ほんまに得意やなぁ」 「あはは、確かにね。でも今年も来れてよかった。このあたりの斜面ってほんとに脆いでしょ、ちゃんと手入れしてないとあっという間に崩れちゃうんだよね」 「もったいないなぁ。オレ、時々ここ来るわ。せっかくええ場所があるんやし、もっと楽しまな」 「うん、来れるうちはがんばりたいよね」 「それにしても、その……何の滝やったっけ」 「華厳の滝と那智の滝」 「それも見たいわ。なんとか行かれんかなぁ」 「……まぁ、そのうち機会があるかもね」 あたしたちの会話に、滝の音が背景のように静かに響いている。何度か風が吹き、木々を揺らしてあたりに落ち葉を散らしていた。 鮮やかな色をしたその葉が風に舞って視界を横切る不思議な雰囲気を、あたしはしばらく楽しんでいた。 日は少しずつ傾き始めていた。あたしは不意に入ってきた冷たい風に小さく体を震わせ、そのときになって、ここでかなりの時間を過ごしていたことにようやく気づいた。 もう帰らないと。暗くなっちゃうよ。あたしがそう言うと、アキオは少し残念そうな表情になった。 帰り道は、崩れやすい斜面を下るぶん、来るときよりもさらに時間がかかる。あたしとアキオはまだいろいろと話しながら歩いているが、少しだけ言葉が少なくなる。 ようやく信号の交差点のところに到着した頃には、あたりは少し薄暗くなっていた。少し疲れが出た足で、今度は店への道を登って行くことに気づいたアキオがげっそりとした顔になるのを見て、あたしはつい、小さく笑ってしまう。 すっかり日が落ちてからようやく店にたどり着き、疲れ顔のアキオはバイクで帰っていった。あたしは店の前に立って、山の向こうの薄れ行く夕焼けの色を見ながらしばらくじっと立っていた。やがてその色も消え、周囲が夜闇に包まれてから、一つ大きく息をついて家の中へと入った。 次の日、あたしが本の配達のついでに病院に寄ると、ちょうどアキオが大池先生と話し込んでいるところだった。 「あれ、アキオ、どうしたの?」 「六甲の街に買い物の帰りや。別に用事言うほどのものやないで」 「ん、ならいいけど。昨日ので怪我でもしてたらどうしようかと思っちゃったからさ」 「そ、それなら大丈夫やわ」 話をしながらあたしは、アキオがどこか機嫌の悪そうにしているのに気づいていた。 なんだろう、と思っていると、大池先生が口を挟む。 「昨日というと、みかげちゃんも一緒に遠出したのかい?」 「あ、うん。ほら、例の紅葉狩り。昨日行ってきたんだ」 「なるほどね、昨日だったのか。アキオ君、遠出というわりに、それほどの距離でもないんじゃないかい?」 大池先生が不意にアキオを見ると、アキオはぎくりとした。不意に立ち上がると、 「オ、オレ、用事あったんやわ。帰るで」 そう言って部屋の外へと歩き始めた。 「ふぅん。まぁ、気をつけて帰りなさい」 なにやら含みのある笑い顔の大池先生がそう言う。あたしはわけがわからず、ついアキオと大池先生を交互に見てしまったが、アキオの歩き方を見ていて不意に、何のことかを理解した。 「あれ、アキオもしかして」 「な、なんや」 「筋肉痛でしょ」 「…………」 あたしがニヤニヤしているのがすぐにわかったのだろう、アキオは憮然とした顔になった。 「そ、それがどないしてん」 「アキオって案外、運動不足なんだ」 「ええやろ。つうか、あれは歩きすぎや。それより、みかげはどうやねん」 「え? あたしは平気だけど? 普段から歩いたり重いもの運んだりしてるしね」 「…………」 アキオはますます不機嫌な顔になる。さすがにあたしは、あまり意地悪するのも可哀想になって来た。 「でもほんとに大丈夫? 怪我とかじゃないよね」 「せ、せやから平気やて。こんなん、二、三日寝とけば治るわ」 「うん、それならいいんだけどね。でもいいじゃない、歩いたお陰でいいもの見られたんだからさ」 「……まぁ、それは確かやわ。ほな、ほんまに帰るで。いくらなんでも、あんまり何時間ものんびりはでけへんねん」 歩き始めようとするアキオを大池先生が、ちょっと待ちなさい、と呼び止め、そばの机に置いてあった白い紙袋を手渡した。 「とりあえず家に帰ったら少し休んで、治まってきたら熱いお風呂に入ってマッサージするといい。それから、寝る前に軽く体を動かすと治るのが速くなるよ。あまりひどかったらこの湿布を使いなさい」 「わかったわ」 「ま、お大事にね」 アキオが病院の玄関から出て、バイクで去ってゆくのを、あたしと大池先生は窓から見送る。その姿はすぐに坂の下へと消えていって、排気音だけがしばらく聞こえていた。 「やれやれ、あの様子ではバイクに乗るのも大変だろうね」 「アキオ、そんなにひどいんだ」 「まだ若いんだから大丈夫だよ。しかし、ぼくも行ければよかったんだがね」 「ごめんね、一緒に行けなくて」 「いやいや、予定が空いていてもぼくは遠慮するよ。あんな山道を歩ききる自信がないし、怪我でもしたらハルナに怒られてしまう」 「ま、まぁ、ハルナだけじゃなくて神戸の人たちみんなが困っちゃうよ」 「それはどうかな……」 不意に大池先生が視線を外に移した。あたしはつられて同じ方を見てしまう。窓の外の木々は、あの滝で見てきた紅葉ほどではないが、そろそろ秋のくすんだ色が見え始めている。 「そうか……もうそんな季節なんだ」 「うん。一年が経つのって速いよね」 「今年はアキオ君が一緒だったんだね。どうしたんだい?」 「あ、うん、出発するときに見つかっちゃってさ。でももしかして、そのほうがよかったのかも。ほら、アキオに見せてあげられたでしょ、滝。あたしだけ独り占めしたままっていうのも、ちょっとあれだったしさ」 「……それはそうだね。あと何年見られるかわからないだろうからね」 「うん……」 「…………」 大池先生は、何か考え込むような表情になった。しばらくしてあたしが口を開こうとすると、その少し前に、不意に大池先生が言った。 「……こうして……藤代先生との思い出も少しずつ失われて行くのかな……」 「…………」 あたしはつい、返事をし損なってしまう。また部屋は静かになる。時々、外の木々が風に揺れる音が聞こえるだけだ。 どのくらいそうしていたのか、また、大池先生が口を開いた。 「まぁ、それが生きていくということなのかもしれないね。昔も思いでの風景が失われることくらいあったろう。昔と今とではずいぶん事情も違うけれど、結局のところ、ぼくたちにとっては大きな差でもないような気がするよ」 「……うん……」 あたしはなにか複雑な思いにとらわれて、なんとなく窓の外を眺めているだけだった。 先生の言うとおり、数日も経つとアキオはすっかり元気になっていた。店にやってきて古い地図を見せてくれと言うので、あたしは倉庫の奥からアキオの希望にあいそうなものをいくつか出してきた。彼が熱心に華厳の滝と那智の滝を探しているのを、あたしは半ば呆れ、半ば感心しながら見ていた。 「ここらもな、いつか行ったるで」 力強く言う彼。あたしはなぜか、先生とあの滝で過ごした日々のことを思い出していた。 一瞬だけ、なにか感傷的な気分になっている。 「ま……」 「なんや」 あたしはその気持ちを振り払うと、手のひらでポンポンとアキオの肩を叩く。 「若いっていいよね」 その言葉に、アキオは一瞬、憮然とした顔になる。 「……ほ、ほんまやで。ほんまに行ったるからな」 「ま、そのときは土産話、よろしくね」 「話だけやのうて、ほんまに土産持って来たる。楽しみにしときや」 彼のその言葉が実現するのはこれから数年もしないうちだったが、あたしにはそんなことを知る余地などなかった。 ただ再び、何か表現しにくい不思議な気持ちだけがあたしの中に残っていた。 |



|
|
注1 華厳の滝: 栃木県日光市にある滝。中禅寺湖から出る大谷川(だいやがわ)にある滝で、落差九十七メートル。昔は水が滝壺へと直接落ちていたが、1986年の大崩落で途中に段ができてしまっている。観光化が激しい滝の一つで、神滝としての雰囲気はかなり殺がれているというのが正直なところ。 注2 那智の滝: 和歌山県の那智勝浦町にある滝。「那智の滝」と言うと正確には那智にある複数の滝のことを指すが、一般には「那智大滝」のことを指す。落差百三十三メートルの日本一の直瀑。熊野の奥地にあることもあり、かつては神聖な雰囲気が強かったが、今では周囲の原生林も切り開かれ、観光地化されているのが残念。 ちなみに、「三大神滝」は確かに「華厳」「那智」「布引」だが、「三大名瀑」と言うと「華厳」「那智」「袋田」になるらしい。 注3 布引の滝の大きさ: 前述の通り、華厳の滝は九十七メートル、那智の滝は百三十三メートルに対し、布引の滝は落差四十三メートル。水量から言っても見劣りすることは確か。 |